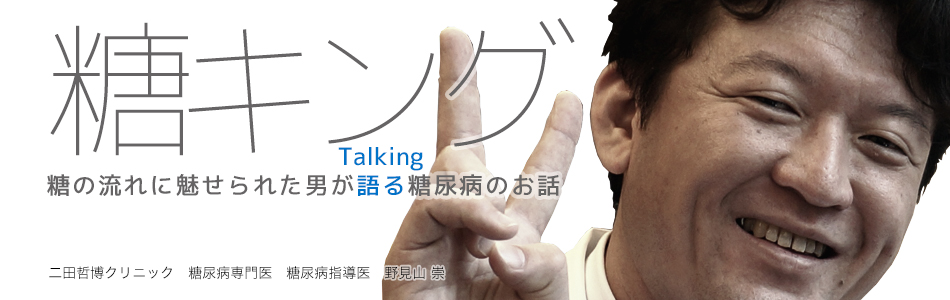
医療人として | 糖尿病の治療について | 糖尿病についてのコラム | プロフィール
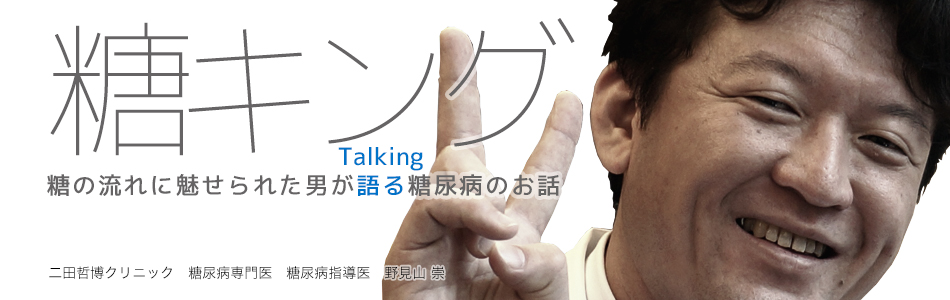
人はとかく物事を“分類”したがる傾向があるようだ。平成元年に大学生となった我々世代が若者の時は“新人類”と言われ、最近の若者世代は“Z世代”などとくくられて世のオジサンたちになじられている。世代間の直接抗争を避けるために“お前はZ世代だから仕方ないな”という一言で終わらせるのも得策かもしれないが、新人類の中にも昭和感満載の風来坊のような友人も居たし、Z世代の中にも我々の若い頃のように“気合い”とか“根性”とう言葉の下に夜露死苦(ヨロシク)ツッパっている若者もいる。つまり、強引なグループ分けは物事やその人の本質を見失う可能性があるという事だ。
同様の現象が今、糖尿病の血管合併症でも起こっている。DKD(Diabetic Kidney Disease)という言葉がある。CKD(Chronic Kidney Disease 慢性腎臓病)という概念もかなり強引だと思っていたが、DKDとは何ものであろうか?最初に耳にした時はDDT(デンジャラス・ドライバー・天龍)に続くDKD(Dangerous Knee Drop)とかいう新しいプロレス業かと思ったが、そうではないらしい。由緒正しい糖尿病の腎臓の合併症である糖尿病性腎症とは違うDKDを日本語で糖尿病関連腎臓病と呼ぶ羽目になった詳しい経緯を、金崎啓造先生が懇切丁寧にきめ細やかに言葉を選んで糖尿病学会誌に解説されている(糖尿病67(2):43~49,2024)。この中に“現時点では病名ではなく、疾病の学問的定義である”という一文がある。という事は、臨床の現場ではDKDという言葉は使用する機会がなく、治療方針の決定や保険診療には関係ないという事か?では何のためにDKDというネーミングが必要なのか?滋賀医科大学第3内科に国内留学していた私は、糖尿病性腎症という正統派の糖尿病による腎臓合併症を研究されて来た吉川隆一先生、羽田勝計先生、古家大祐先生らのご尽力と素晴らしい研究成果を肌身で感じて育った。降って湧いて出たDKDではなく糖尿病性腎症という病名と病態を大切にしたい。北里大学の守屋達美先生は私と同じ御意見の様で、大変嬉しく思う(Medical Science Digest 48巻2号,68-72,2022)。病理がご専門の守屋先生は、病理学的に異なるものを同じ疾患群にひっくるめるのはいかがなものかとご指摘なのであろう。私も同感だ。病態病理が歴然としない雰囲気でつけられた病名は混乱を招き、誤った処方や治療につながりかねないと個人的に考える。
しかし、合併症・併存疾患の研究に重きを置いて来た私としては、DKDという言葉が流行ることによって、糖尿病の血管合併症に注目が集まり、腎症を含む細小血管合併症や動脈硬化性疾患をしっかりケアしてくれる医師が増えることは嬉しいことだ。一方で、DKDが独り歩きして尿アルブミンを測定しない医師が増えてきていることは大問題である。最近頂いた紹介状に“糖尿病性腎症のステージはG3bです”と書いてあった!!??(注:G3bはCKDのステージで糖尿病性腎症のステージではありません)そんな中、尿アルブミン測定の重要性を痛感させられる素晴らしい報告がある。九州大学ご出身で、現在帯広で御開業の横山宏樹先生は、実臨床に即したJDDMという素晴らしい御研究を継続されておられる。まさに日本のUKPDSと言っても過言ではない。私も一度講演に呼んで頂いたことがあるが、豪快で素晴らしい人物の先生だ。JDDM54では、糖尿病のある人を腎臓の状態で4群に分けると、DKDやCKDの指標とされるeGFRに問題がなくとも尿アルブミンが糖尿病性腎症第2期レベル以上出ている人は、将来心血管疾患を起こす可能性が高いことが示された(Diabetes Care. 2020 May;43(5):1102-1110)。一方で、eGFRがDKDの範疇でも尿アルブミンが出ていない人は血管予後が健常腎の人と全く同じであった(図A)。さらに、後にeGFR≦30の末期腎不全になる予測因子としてもeGFRよりも尿アルブミンが優れた指標であることが同時に示されている(図B)。すなわち、eGFRだけ測定してDKDじゃないから大丈夫だと思っていると、糖尿病のある人の血管病を見落とし、10年後に取り返しのつかないことになる。糖尿病のある人にとって、eGFRはメトホルミンの用量を決めるなどの腎予備能の指標にはなるが、血管病変の進行は検出できない指標と言える。尿アルブミンこそが早期から糖尿病のある人の血管病変を検出できる“心血管の鏡”と言える。
尿アルブミンは毎月測定すると保険診療上査定を受ける。3ヶ月に1回以下の測定とすることが義務付けられている。厳しい地域やクリニックでは日数単位で査定されるとの噂も聞いたことがあり、我々の改訂した連携手帳(第28話)が新しい見開きページになったら測定して頂けると良いのではないか。第53話でも紹介した死因アンケート調査(糖尿病67(2):106-128, 2024)の結果では、非糖尿病の人に比べて糖尿病のある人は血管障害で亡くなるリスクが低かった(表)。しかし、詳細に見てみると脳血管障害で亡くなる人は減少しているが、虚血性心疾患や腎不全で亡くなる人は糖尿病の人の方がいまだに高率である。これらを減らすためにも、尿アルブミンを測定して血管状態を把握し、血管障害に早期介入する必要がある。
<残心>卒後30年
私は平成7年(1995年)に順天堂大学医学部医学科を卒業しました。平成7年は阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件など大惨事が相次ぎ、日本がひっくり返っている時に医師になった事を覚えています。今年2025年はあれから30年が経ちます。長い様で短いような、何がどうなったのか系統だって思い返せないような30年でした。もし、デロリアンに乗って30年前の自分に会えたら未来の自分として何と伝えるでしょう。よく分かりませんが、糖尿病学の道を選んだことは間違いないと胸を張って言えます。我々の卒後30年、糖尿病学の進歩は目覚ましく治療薬も格段に良くなりました。糖尿病は循環器内科や腎臓内科が片手間に診る疾患と言われていたのが、一躍メジャー疾患になりDKDという概念をひねり出して糖尿病学に縋り付こうという動きが出るくらいです。そんな30年を実体験として知る平成7年卒の同期で、現在教授職にある3人で座談会をしました。私と神谷英紀先生、古橋眞人先生の3人が同期のサクラとして本音で語る糖尿病学30年が医学書院の内科臨床誌メディチーナ2025年1月号に収められています。特に若い先生方に是非読んで頂きたい。本誌の企画編集は私が担当しており、二田哲博クリニック姪浜院長の下野大先生にもご執筆頂いています。
2025年が災害や争いのない平和な年であることを心からお祈りします。
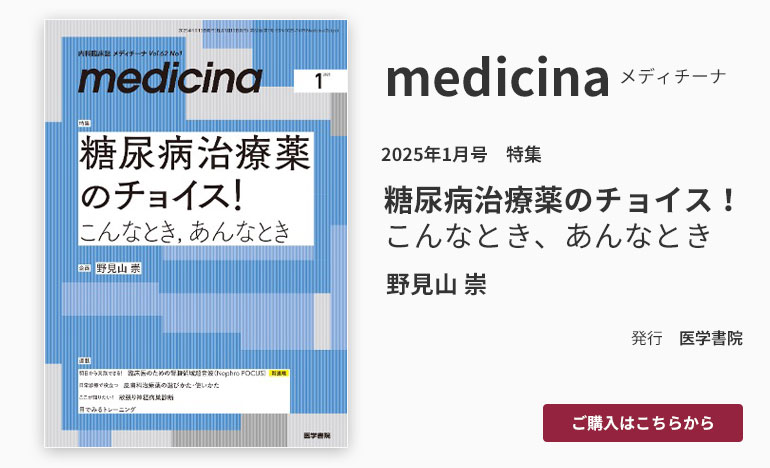
【残心(ざんしん)】日本の武道および芸道において用いられる言葉。残身や残芯と書くこともある。文字通り解釈すると、心が途切れないという意味。意識すること、とくに技を終えた後、力を緩めたりくつろいでいながらも注意を払っている状態を示す。また技と同時に終わって忘れてしまうのではなく、余韻を残すといった日本の美学や禅と関連する概念でもある。(Wikipediaより一部抜粋・転載)
【第01話】多くの人生を変えたミラクルドラック・インスリン
【第02話】HbA1cの呪縛
【第03話】糖尿病と癌
【第04話】糖毒性という名のお化け
【第05話】医者らしい服装とは?
【第06話】食後高血糖のTSUNAMI
【第07話】DMエコノミクス
【第08話】インクレチンは本当にBeyondな薬か?
【第09話】守破離(しゅ・は・り)
【第10話】EMPA-REG OUTCOMEは糖尿病診療の世界を変えるか?
【第11話】新・糖尿病連携手帳
【第12話】過小評価されている抗糖尿病薬・GLP-1受容体作動薬
【第13話】ADAレポート2016
【第14話】メトホルミン伝説
【第15話】Weekly製剤を考える
【第16話】糖と脂の微妙な関係
【第17話】チアゾリジン誘導体の再考~善とするか「悪とす」か~
【第18話】糖尿病患者さんの死因アンケート調査から考える
【第19話】Class EffectかDrug Effectか
【第20話】糖尿病治療薬処方のトリセツ執筆秘話
【第21話】大規模臨床試験の影の仕事人
【第22話】低血糖の背景に、、、
【第23話】ミトコンドリア・ルネッサンス
【第24話】血管平滑筋細胞の奥深さ
【第25話】運動療法温故知新
【第26話】糖尿病アドボカシー
【第27話】GLP-1の真の目的は何か
【第28話】糖尿病連携手帳 第4版
【第29話】残存リスクを打つべし!
【第30話】糖尿病という病名は変更するべきか
【第31話】合併症と併存症
【第32話】メディカルスタッフ
【第33話】新・自己管理ノート
【第34話】グルカゴン点鼻薬とスナッキング肥満
【第35話】SGLT2阻害薬 For what?
【第36話】血糖値と血糖変動のアキュラシー
【第37話】経口GLP-1受容体作動薬
【第38話】コロナ禍をチャンスにする糖尿病診療
【第39話】HbA1cはウソをつく、こともある
【第40話】糖尿病治療ガイド2022-2023:私のポイント
【第41話】順天堂大学医学部附属静岡病院
【第42話】2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム
【第43話】降圧薬のBeyond
【第44話】糖尿病治療はデュアルの時代
【第45話】兄貴に捧げるラストソング
【第46話】血糖だけにこだわらない!糖尿病治療薬の考え方・使い方
【第47話】糖尿病は治るのか?
【第48話】2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム(第2版)
【第49話】医師の働き方改革
【第50話】GLP-1受容体作動薬のセレクト
【第51話】肥満症の治療薬
【第52話】Dear ケレンディア
【第53話】高齢ダイアベティスの極意~キョウイクとキョウヨウ~
【第54話】尿アルブミンは心血管の鏡
【第55話】SGLT2阻害薬 For what?第2章
【第56話】“あいうえお、かきくけこ、さしすせそ”
【第57話】JADEC連携手帳 第5版
【第58話】12th JADEC年次学術集会
【第59話】腫瘍糖尿病学
【第60話】2025th WDD
【第61話】GLP-1RA vs. SGLT2Iどっちが血管保護してる?
*文章、画像等を無断で使用することを固く禁じます。
医療人として | 糖尿病の治療について | 糖尿病についてのコラム | プロフィール
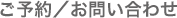 ご質問や不安なことがあればおたずねください。
ご質問や不安なことがあればおたずねください。092-883-1188姪浜(代表)
診察日の9:00~13:00 15:00~17:30
ques@futata-cl.jpお返事に時間を頂いてます。